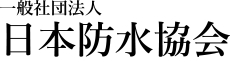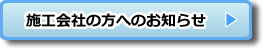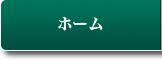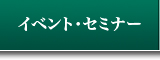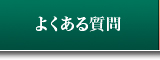酷暑には特に気を付けたいマンションの屋上やバルコニーの「浮き」

「浮き」とは、防水層(ウレタン・シート・塗膜など)と下地コンクリートとの間に隙間や空気が入り、防水材が部分的に剥がれたり膨らんだりしてしまう状態を指します。見た目には軽微な変化ですが、放置すると深刻な漏水事故につながる危険性があるため注意が必要です。
1.高温期に「浮き」が増える理由
① 熱膨張による応力集中
屋上やバルコニーは、日中の直射日光で表面温度が60~70℃以上にもなることがあります。これにより、防水層が熱で膨張します。ところが、下地であるコンクリートやモルタルとの膨張率が異なるため、接着面に応力(引っ張り力)が集中し、密着していた防水材が剥がれることで“浮き”が発生します。
② 既存の劣化が進行しやすい
特に築年数が経っていたり、防水改修から10年以上経っている物件では、防水層の接着力自体が劣化しているケースも多く、そこに猛暑による熱膨張が加わると、わずかな隙間から空気や水蒸気が入り込み、内部で膨らみや剥がれを起こします。
③ 温度変化の繰り返しによる負荷
猛暑の昼間に高温になった屋上も、夜間は一気に気温が下がります。この膨張・収縮を毎日繰り返すことで、防水層は次第に内部から“浮きやすい状態”になります。
2.「浮き」の放置が招くリスク
一見小さな浮きでも、「まだ漏れていないから大丈夫」と放置すると、次のような深刻な事態を引き起こします。
① 雨水の侵入→内部劣化・漏水へ直結
浮いた部分には隙間ができており、雨水が入り込むルートになります。一度でも強い雨や台風が来れば、防水層の下に水が浸入し、下地を侵食。やがてコンクリートのクラック(ひび割れ)や鉄筋の腐食、室内天井からの漏水事故につながるおそれがあります。
② 防水層の全面劣化を早める
浮きのある部分は、踏圧(人が歩く、風圧を受ける)や熱でさらなる剥離や破断が起こりやすくなります。つまり、一箇所の小さな浮きが連鎖的に周囲へ広がり、数年以内に全面改修が必要になるリスクを高めます。
③ 修繕費用が膨れ上がる
初期の段階であれば、部分補修(数万円〜十数万円)で済むものが、放置することで防水層全体の張り替えや屋上全面工事(数十万〜百万円単位)が必要になる可能性があります。浮きの放置は、結果的に修繕コストを数倍に膨らませる判断ミスなのです。
3.オーナー様や管理会社が取るべき「浮きへの即時対応」とは?
① 浮きの発見=すぐ専門業者へ連絡
浮きが小さいうちに対応することで、補修は非常にシンプルになります。
・浮き部分の切開・接着剤注入・再加圧
・トップコート塗布や簡易シールで保護
・必要に応じて部分的な張替え
いずれも、早期発見なら短工期・低予算で済むのが特徴です。
②点検する際のポイント
自らが屋上に出る際には、以下のような点をチェックしてみてください。
・歩いてみて“フカフカ”“ポコポコ”とした感触はないか
・表面にふくらみ・波打ちがないか
・表面に色ムラ(中の空気の影)が見えないか
・雨のあとは一部に水たまりができていないか
1つでも該当すれば、浮きの兆候が出ているサインです。