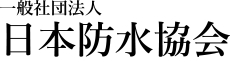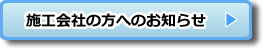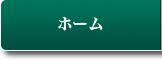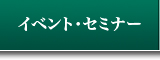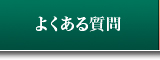月: 2022年7月
コラム追加: 裁判例から学ぶ。押さえるべきポイントを紹介! 「施工業者の不始末!責任は誰が負うの?」
コラム追加:防水工事の種類と流れ① <ウレタン防水工事>
防水工事、はじめの一歩 <オーナー様や管理会社様が知っておきたい基礎知識>
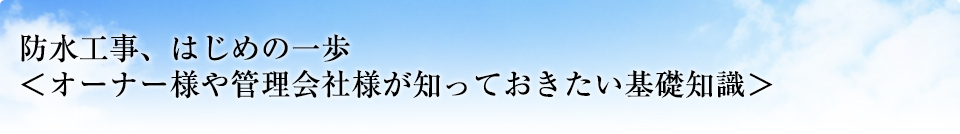

①建物の強度を保つ
→漏水は、建物全体の耐久性を著しく低下させます。
②建物の外観(見た目)や内観(性能や快適性)を保つ
→雨水は建物内外のさまざまな部分に染みや変色を生じさせて見た目を損ねます。
③カビを防ぐ(アレルギー疾患を未然に防ぐ)
→漏水している箇所の周辺ではカビが発生し、ぜんそくなどのアレルギーを引き起こす可能性があります。
●木材:腐食
●鉄:錆び
●コンクリート:中性化が進む※
●鉄筋コンクリート:中の鉄骨が錆びる
※コンクリートのひび割れなどのトラブルを引き起こす
①ウレタン防水工事
ベランダや屋上の床に液体状のウレタン樹脂を床面に厚めに塗り拡げて乾燥させ防水膜をつくる工法です。ビルやマンションといった大規模な建物の屋上から一般住宅における平面状の屋根まで施工できます。
②アスファルトシート防水
合成繊維不織布のシートに液状に溶かしたアスファルトを染み込ませコーティングする工法です。広い場所への施工が適しているため、学校やマンション・公営住宅などの屋上や屋根で採用されることが多くなっています。
③FRP防水
FRPとは、繊維強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastics)の略称であり、木やコンクリートで作られた床の上にFRPのシートを敷き、その上に樹脂を塗って硬化させる工法です。
④塩ビシート防水
塩化ビニル樹脂が素材のシートを使う工法です。塩ビシートは、元から着色されているので、通常の施工で必要とされている仕上げ材の塗装が必要ありません。
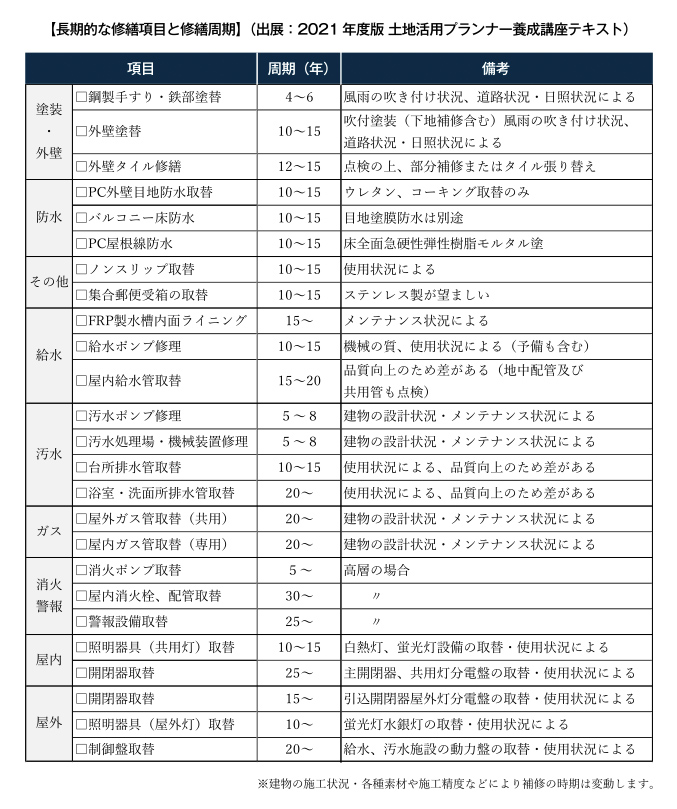
防水工事の種類と流れ① <ウレタン防水工事>
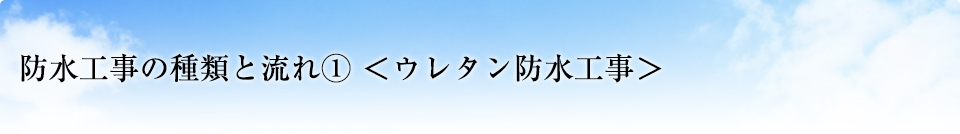
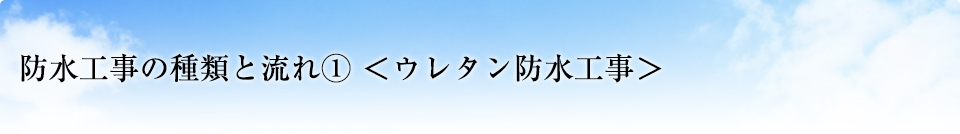
①塗る回数のごまかし
②乾燥時間の短縮
③防水シートの繫ぎ目の接着がしっかりとしていない
①密着工法
→床面に直接ウレタン樹脂を塗るシンプルな工法。
②メッシュ工法
→床面にメッシュシートを貼り付けてウレタン樹脂を塗る工法。密着工法よりもヒビ割れしにくい。
③通気緩衝工法
→床面に直接ウレタン樹脂を塗らず、床面に敷いた通気緩衝シートの上から塗り固める。
①高圧洗浄…高圧の水で表面の汚れを取り除きます。
▼
②清掃…表面に残ったゴミや不要な防水層などを掃除します。
▼
③ひび割れなどの補修…ひび割れクラックを補修すると共に凹凸を平にします。
▼
④ドレンの設置…雨水を流すためのドレン(排水溝)を設置します。
▼
⑤プライマーの塗布…下地と防水材を密着させるためにプライマー(接着剤)を塗ります。
▼
⑥パラペットのウレタン防水…パラペット(屋上やバルコニー等の外周部に設置された低い手すりのような部位)の防水施工を行います。
▼
⑦ウレタン塗膜の下塗り…1層目のウレタン塗膜を塗布します。
▼
⑧ウレタン塗膜の中塗り…2層目のウレタン塗膜を塗布します。
▼
⑨トップコート塗布…ウレタン塗膜の劣化を防ぐための保護塗料を塗布します。
▼
⑩密着工法完了…作業は全体を通して3日~5日で完了します。
密着工法の①から⑤の流れの後にメッシュシートを貼り、⑧「ウレタン塗布の中塗り」に移行します。
①高圧洗浄…高圧の水で表面の汚れを取り除きます。
▼
②清掃…表面に残ったゴミや不要な防水層などを掃除します。
▼
③ひび割れなどの補修…ひび割れクラックを補修すると共に凹凸を平にします。
▼
④プライマーの塗布…下地と防水材を密着させるためにプライマー(接着剤)を塗ります。
▼
⑤通気緩衝シートの貼り付け…下地に含んだ雨水や水分を逃がすためのシートを貼り付けます。
▼
⑥ジョイントテープの貼り付け…シートのジョイント部分にテープを貼ります。
▼
⑦ドレンの設置…雨水を流すためのドレン(排水溝)を設置します。
▼
⑧脱気筒の設置…下地に含んだ水分を脱気筒から外に排出します。
▼
⑨パラペットのウレタン防水…パラペットの防水施工を行います。
▼
⑩ウレタン塗膜の下塗り…1層目のウレタン塗膜を塗布します。
▼
⑪ウレタン塗膜の中塗り…2層目のウレタン塗膜を塗布します。
▼
⑫トップコート塗布…ウレタン塗膜の劣化を防ぐための保護塗料を塗布します。
▼
⑬密着工法完了…作業は全体を通して5日~7日で完了します。
裁判例から学ぶ。押さえるべきポイントを紹介! 「施工業者の不始末!責任は誰が負うの?」
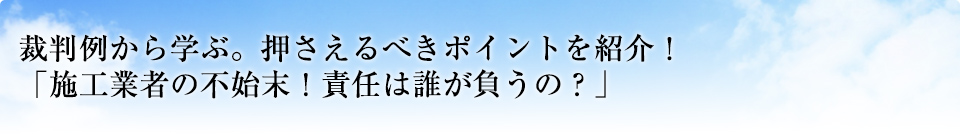

施工業者の不始末により発生した漏水事故について、賃貸人は賃借人に対し賃貸借契約に基づく債務不履行責任を負うのか。
施工業者の不始末により発生した漏水事故について、当該居室の所有者は、入居者に対して工作物責任(民法717条1項但書)を負うのか。
施工業者の不始末により発生した漏水事故について、施工業者及び賃貸管理業者は責任を負うのか。
弁護士 原田 宜彦
首都大学東京(現 東京都立大学)法科大学院修了
著作:『実例と経験談から学ぶ資料・証拠の調査と収集-相続編-』(共著)他
講演:(公社)東京共同住宅協会主催 「第11回土地活用プランナー養成講座」(2020年8月)他